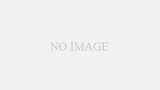東京都文京区本郷三丁目Personal taining studioカメシチ
ダイエット&脚やせトレーナーの吉田尚弘です。
1. 果糖とは?甘みの強い糖の特徴と摂取源
果糖(フルクトース)は単糖の一種で、果物、蜂蜜、砂糖(ショ糖)の構成成分として自然界に存在しています。特に甘味が強いため、食品産業では清涼飲料水や菓子類に用いられる高果糖コーンシロップ(HFCS)として頻繁に使用されます。
出典:
-
日本食品標準成分表2020年版(八訂)
-
「果糖とは何か?」 厚生労働省 e-ヘルスネット
2. 肝臓に負担をかける果糖の代謝と肥満・脂肪肝リスク
果糖はブドウ糖と異なり、筋肉や脳では使われず主に肝臓で代謝されます。余剰な果糖は中性脂肪に変換され、肝臓内や内臓に脂肪が蓄積しやすくなります。これが肥満や非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)につながる可能性があります。
さらに果糖は、インスリンの分泌を必要としないため血糖値を急激に上げにくい反面、インスリン抵抗性を進行させ、糖尿病の発症リスクにも影響を与えることが知られています。
出典:
-
「果糖がもたらす肝機能への影響」糖尿病ネットワーク
-
「果糖が特に健康に悪いといわれる理由」Geefee 栄養と科学
3. 腸内環境のバランスを崩す果糖の影響
果糖を多く摂取する食生活は、腸内細菌叢(腸内フローラ)を乱す可能性があります。特に高果糖食は、善玉菌の減少と悪玉菌の増殖を助長し、腸内の炎症やバリア機能の低下につながることが報告されています。
腸の透過性が高まる「リーキーガット」が進行すると、腸内細菌や毒素が血中へ移行し、慢性炎症の原因となるリスクがあります。
出典:
-
「果糖が腸内環境に与える影響」国立健康・栄養研究所
-
「果糖と腸内環境の関係」フローラ健康科学研究所
4. 免疫系の働きを乱す可能性も
高果糖食は、免疫細胞の炎症反応を促進する可能性も示唆されています。たとえば、果糖は樹状細胞やマクロファージの活性を変化させ、慢性的な炎症反応や免疫力の低下につながるとする研究もあります。
免疫力が落ちることで、ウイルスや細菌への抵抗力が弱まり、体調を崩しやすくなるという悪循環も起こりえます。
出典:
-
「果糖の多い食事と免疫系の炎症の関係」Interphoenix ヘルスサイエンス
5. 果糖を過剰に摂らないためにできること
果糖の摂取を過度に避ける必要はありませんが、過剰摂取を防ぐ工夫は必要です。日常生活で取り入れやすい対策には以下のようなものがあります:
-
清涼飲料水・加工食品を控える
果糖を多く含むソフトドリンク、ドレッシング、加工スナックをなるべく避ける。 -
食材の成分表示を確認する習慣をつける
「果糖ブドウ糖液糖」「異性化糖」と書かれていないか確認しましょう。 -
“自然な甘さ”にも注意を払う
果物や蜂蜜も適量ならOKですが、連続して摂取し続けると糖質過多になることも。
出典:
-
「食生活に潜む果糖とそのリスク」Geefee 栄養と科学
-
日本糖尿病学会「食品交換表2020」
6. まとめ|甘さとの付き合い方を見直すきっかけに
果糖は、身近な食品に含まれた自然な甘みでありながら、摂取量によっては代謝・腸・免疫にさまざまな影響を与えます。
食事は楽しみの一つであるからこそ、体調の変化や日々の疲れが気になるときは、「無意識に摂っている糖」に目を向けることもひとつの方法です。
今の自分の体調は、日々の小さな選択の積み重ねからできている。
そんな視点で、「甘さ」と向き合うきっかけになれば幸いです。
自分の体に合った甘さとの付き合い方を見つけたいと感じたら、一人で抱えずに専門家に相談するのも選択肢の一つです。
👉 管理栄養士&ピラティストレーナー吉田が運営する Personal training studioカメシチでは、体の内外からのアプローチでサポートを行っています。