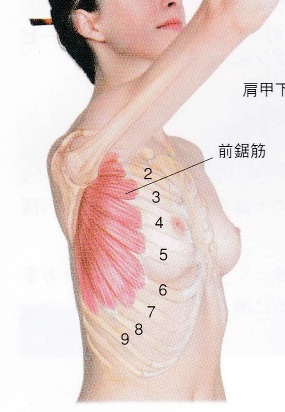東京都文京区本郷三丁目Personal training studioカメシチ、管理栄養士&ピラティストレーナーの吉田尚弘です。
「何をしても痩せにくい…」
「血糖値が高くなってきて不安」
そんな悩みを抱えていませんか?
実はそれ、腸内細菌のバランスが関係しているかもしれません。中でも今、世界的に注目されているのが「アッカーマンシア(Akkermansia muciniphila)」という腸内細菌です。
このアッカーマンシア、実は肥満予防や糖尿病の改善に深く関わっており、食事や生活習慣で増やすことができるんです。今回は、アッカーマンシアの働きと、それを味方につける具体的な食材・調理法について詳しく解説していきます。
アッカーマンシアとは?腸の“番人”とも呼ばれる善玉菌
アッカーマンシア・ムシニフィラ(Akkermansia muciniphila)は、人間の大腸内に生息する善玉菌の一種です。
特徴的なのは、腸の内側にある粘膜(ムチン層)を分解してエネルギー源にしているという点。これにより、腸の粘膜を活性化させ、バリア機能を強化します。
この粘膜が健康だと、外部からの悪玉菌や炎症物質(LPS:リポ多糖)をシャットアウトできるため、腸内環境が整い、全身の代謝や免疫が安定しやすくなるのです。
アッカーマンシアと肥満:腸内から“太りにくい体質”をつくる
肥満の人の腸内を調べると、アッカーマンシアの量が著しく少ないということが多くの研究で明らかになっています。
腸内環境が乱れると、粘膜が薄くなり、腸から炎症物質が血液中に漏れ出す(リーキーガット)現象が起きやすくなります。これが慢性炎症→脂肪の蓄積につながり、太りやすい体質になってしまうのです。
アッカーマンシアはこの粘膜を保護することで、脂肪細胞の過剰な肥大化を防ぎ、脂肪蓄積を抑制してくれます。つまり、“太らない腸”をつくるサポーターなんです。
アッカーマンシアと糖尿病:インスリンの効きやすさに関与
糖尿病(特に2型糖尿病)の発症に大きく関わるのが「インスリン抵抗性」です。これは、インスリンは出ているのに、血糖を細胞が取り込めない状態を指します。
ここでもアッカーマンシアが活躍。腸内の炎症や粘膜障害がインスリン抵抗性を引き起こすことが知られており、アッカーマンシアがそれを改善することが複数の研究で示されています。
特に有名なのが、2019年に行われたDepommierらによる臨床研究。
アッカーマンシアを加熱処理してカプセル化したものを12週間摂取したグループは、インスリン感受性が有意に改善され、血中の中性脂肪や肝酵素(ALT)も低下しました。
しかもこの効果は、「生きた菌」よりも「加熱処理された菌」のほうが高かった、という驚きの結果でした。
アッカーマンシアを自然に増やす食材とは?
現在、日本ではアッカーマンシアのサプリメントは市販されていませんが、自分の腸にいるアッカーマンシアを食事で増やすことは可能です。
以下に、研究でも注目されている“アッカーマンシアを育てる”食材をご紹介します。
✅ 水溶性食物繊維を多く含む食材
- ごぼう、玉ねぎ、大豆、チコリ、バナナ、アボカド、寒天 など
→ 腸内の善玉菌のエサになる「イヌリン」「フラクトオリゴ糖」が豊富
✅ ポリフェノールを含む食品
- ブルーベリー、ラズベリー、クランベリー、カカオ(高カカオチョコ)、緑茶、赤ワイン(少量)
→ 吸収されにくいため大腸に届き、アッカーマンシアの増殖を助ける
✅ 発酵食品
- 味噌、ぬか漬け、納豆、キムチ、ヨーグルト
→ 腸内全体の環境を整えることでアッカーマンシアの定着に貢献
調理法と食べ方の工夫:アッカーマンシアを応援する日常の工夫
アッカーマンシアを育てるためには、食材の“食べ方”も大切です。
☑ 加熱しすぎない
- ポリフェノールやオリゴ糖は熱に弱いため、蒸し調理・短時間加熱が理想
☑ 皮ごと使う
- ごぼうやりんご、なすなど、皮の部分に食物繊維が集中。できるだけ皮つきで調理を
☑ 冷やしてレジスタントスターチを増やす
- 炊いたごはんを冷やすと、腸まで届く“難消化性デンプン”が増え、アッカーマンシアのエサになる
☑ 間食で腸内をリセット
- 食事の合間に、素焼きナッツや干し芋、バナナとヨーグルトなど腸にやさしい間食を
アッカーマンシアを活かす「腸活×血糖コントロール」の習慣
アッカーマンシアを増やすには、食事だけでなく、生活全体のバランスも欠かせません。
- 運動習慣(特にウォーキングやピラティス):腸のぜん動運動を活性化
- 睡眠:成長ホルモンや自律神経のバランスが腸内細菌に影響
- ストレス:腸と脳はつながっており、ストレスは腸内フローラを乱す最大要因
当スタジオでは、ピラティスを通じた内臓アプローチや、自律神経を整えるプログラムもご提案しています。
アッカーマンシアを味方にすれば、もっと楽にダイエットできる!
「ダイエットは食事制限だけではない」
「糖尿病予防は薬だけではない」
私たちの体には、本来「健康を取り戻すチカラ」が備わっています。その鍵を握るのが“腸”であり、そこにいるアッカーマンシアのような微生物たちなのです。
今の食生活に少し意識を向けて、ごぼうやブルーベリー、発酵食品を取り入れてみてください。
腸が変わると、体も気分も自然に整っていきますよ。
Personal training studioカメシチでは、腸活・栄養指導・ピラティスを通じて、皆さんの“根本から変わる体づくり”をサポートしています。気になる方はぜひトライアルへ!